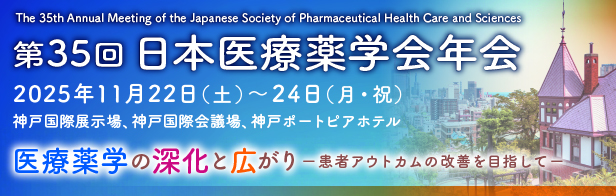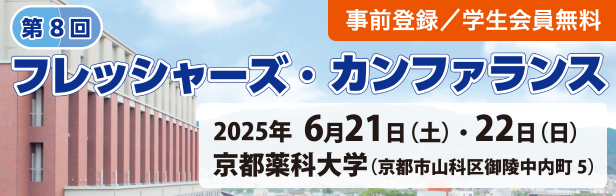2025年2月4日
一般社団法人日本医療薬学会
2024年度医療薬学学術第2小委員会
2019年11月に医療薬学学術第一小委員会より「医療現場における薬物相互作用へのかかわり方ガイド」が発表され、厚生労働省のガイドラインと添付文書の記載要領改正も踏まえて、医療現場において薬物相互作用をどのように評価し、マネジメントすれば良いかという基本的な考え方が示されました。さらに、医療薬学学術第四小委員会では、COVID-19感染拡大時に、「パキロビッド(ニルマトレルビル/リトナビル)の薬物相互作用マネジメントの手引き」(2022年2月28日)および「ゾコーバ(エンシトレルビル)の薬物相互作用マネジメントの手引き」(2023年1月19日)を公表し、広く活用されています。しかし、このような薬物相互作用マネジメントの支援活動を特定の薬剤に限らずに継続的に行っていくこと、そのために必要な情報をアップデートしていくこと、不足している情報を補強していくこと、薬剤師のマネジメント能力を育成することが、医療現場における適切な薬物相互作用マネジメントの質向上とその普及のために重要な課題です。そこで、これらの課題の解決に向けて、医療現場における適正な薬物相互作用マネジメントのための包括的基盤を構築することを目的に2024年度医療薬学学術第2小委員会として活動が開始されました。その活動の一環として、今般「代謝酵素(P450分子種)とトランスポーターを介する相互作用において留意すべき薬物のリスト」を作成しました。本リストは、ガイドラインの基準1, 2)に基づいて主な国内承認薬を分類したものです。上述のガイドや手引きと併せてこの表の有効活用を希望するとともに、前文および各表に記載した注意点を必ず参照するようにお願いします。
本学会会員のみならず、病院、薬局、在宅などの医療現場で活躍される皆様に、本リストをご活用いただければ幸いです。
参考資料
1. 「医薬品開発と適正な情報提供のための薬物相互作用ガイドライン」について (薬生薬審発 0723 第4号,平成30年7月23日)
2. 薬物相互作用試験に関するガイドラインについて (医薬薬審発 1127 第2号,令和6年11月27日)
<本件に関するお問い合わせ先>
一般社団法人日本医療薬学会 事務局
E-mail: inquiries@jsphcs.jp